1. 学校について
・船っ子教室・放課後ルームにおける体育館利用
・学校徴収金の徴収・管理
2. 障がい児支援について
・医療的ケア児等への支援
・児童発達支援
・特別支援学校スクールバスの運行管理
3. 子ども達の活躍の発信について
4. 金杉川、北谷津川上流の再生・保全について
5. 医療センター移転・建替えに向けて
医療センター移転・建替えに向けて
報道によると、松戸市長は
「地域医療の在り方を踏まえた上で、必要なプランを少し見直す考えはある」(朝日新聞)
「3年目までには入札と着工をやり遂げたい」(東京新聞)
6月、柏市との連名で「公立病院建て替え及び経営に関する要望書」提出の際には、建て替え費用を「自治体だけで負担するのは限界」(読売新聞)との
コメントが掲載されていました。
- これ以上負担する考えはないということでしょうか?
柏市は、概算工事費が基本計画時は約132億円、基本設計時は225億円から、施工予定者選定時は約290億円となったことを受け「最大限の経営努力により収益を確保したとしても工事費返済のための支出に追いつかず、極めて経営の困難な状況を生じかねないものです。したがって、何も策を打たなければ経営破綻の危機を生じさせかねないことから、持続可能な病院の経営を確保するためには病院存続のための抜本的な解決策の導入の判断が迫られている段階であると考えている」、実施設計の段階で建物の仕様や面積を見直す方針、と議会答弁しています。
柏市は指定管理者の運営、2次救急、診療科目、病床数も違いますが、市がこのまま進めることに病院経営破綻の危機感を持っています。
- 病院経営の先行きは不透明です。すでにR6の病院事業決算見込みは-10.8憶円です。今後、建替えを含めた持続可能な経営判断の基準は?
- 病床規模や建物の仕様など見直すことも含めた検討も視野にあるのか?
- 医療センターの建替え・移転について今後、どのように検討を進めていくのか?

物価高騰の中で、全個室の公立病院は理解が得られないと考えます。
選挙を経て市民の関心はさらに高まりました。透明性をもって事業実施経過を市民にも分かるよう、理解を得られるような進め方を要望する
学校徴収金回収システム「学校モール」「スクペイ」
教材費や学級費などは、学校ごとに徴収管理をしています。徴収金額は、学校や学年によって様々ですが、我が子の学校でいえばおおよそ年間2万円~5万円程度、3回徴収しています。
国では「学校徴収金の徴収・管理については、基本的に学校以外が担うべき業務」として、地方公共団体が担い学校の負担軽減を図る取組みの推進を求めています。しかし、船橋市での認識は鈍く、学校単位で学校徴収金の納入方法に代金回収サービス「学校モール」「スクペイ」などを利用する動きがあります。
⑴ 市内の導入状況
→学校モール 小学校16校 中学校3校
スクペイ 小学校7校 中学校1校
コンビニ収納 小学校11校 中学校1校
保護者懇談会時に通帳持参させ、その場で徴収システムに登録をしたという学校も。よく分からないまま口座番号、暗証番号を入力し登録を余儀なくされたが、その後になって個人情報流出を懸念する声が出ています。
個人情報流失の責任はサービス会社としますが、不安は拭えません。
教員の負担軽減を図ることには賛成です。しかし、このサービスには個人情報だけではなく、年間費があります。契約によって違うようですが、我が校でいえば1人年間550円、一回の引き落としに100円です。3人いたら、支払うだけで年間2,000円以上を負担です。口座登録に失敗したらまた別途お金が掛かる仕組みです。システム利用に係る年間費、引き落とし代金負担分は、教材費で調整し、例えば、紙のドリルからAIドリルに代えるなどして、保護者からの徴収金額は同等とする工夫をしている学校もあります。
郵便局の口座引落しには1回10円程度、金融機関だと100円程度にはなりますが、持参債務の原則から振込手数料の保護者負担は理解できます。しかし教員の負担軽減のための経費(つまり、年間手数料)を保護者が負担するのはおかしいと考えます。
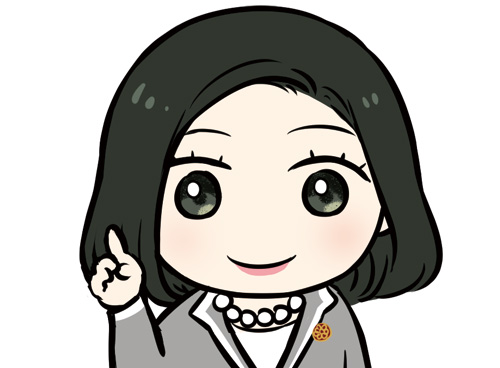
事の発端は国からの「学校の負担軽減を図る取組み」であり、保護者ニーズではない。教育委員会は、保護者側にも支払い方の選択が広がるのは年会費を払うに値するメリットがあるとしますが、そうとは思えないし、子ども達の教材費が削られています。必ずしも口座振替を利用できる家庭が全てではないし、登録しない家庭もある。校外学習や修学旅行など別途徴収があり、一本化にはならない。システムを利用する学校、利用しない学校がある。学校動向に注視するのではなく、市として取り組む必要がある。そもそも国は、「地方公共団体が担っていくべき」としています。
活動報告№68









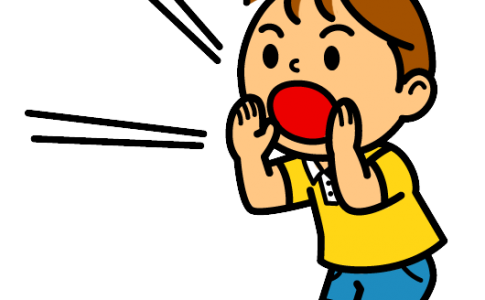




プラン作成から10年以上経過している。医療センターの機能・規模、財政状況も含めて検討する。